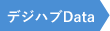レポート作成日:2025/07/25
第17回課題深掘り会レポート【ナラ枯れ桜枯れの被害をデジタルの力で食い止めたい。】
課題について
・ナラ枯れは、「ナラ菌」と呼ばれるカビの仲間の病原菌を昆虫が運ぶ、いわば伝染病。
・県内では、県南を中心に被害が急拡大しており、県北にも進行中。
・ナラ枯れは被害が出てから対策をしても遅いので、まだ被害が少ないうちに対策していくことが必要であるが、人手が足りない。
・ドローンで撮影した画像や座標データなどで、対策が必要なナラの状態や場所を確認することができれば、林業従事者が動けるのではないか。
・桜や梅、モモの木も、特定外来生物のクビアカツヤカミキリの影響で、すごいスピードで枯れている。
・まだ被害が拡大していない段階で効果的な対策を行い、どうにか進行を止めたい。
・なぜ効果的な対策が進まないのかについては、ナラは有用樹ではないということが要因の一つにあると思う。桜などは有用樹なので守ろうという意志が働くが、ナラはそうではないので、なかなか熱量がなかったり、優先順位が上がらなかったりするのではないか。
課題の深掘り
・木を枯れさせる原因の虫はどうやって殺虫するのか?
→虫がいる木を切ってシートで包んで燻す(もしくはそのまま燻す)方法と、チップを作るのと同じように虫ごと粉砕する方法がある。
・虫が木に入るために掘る穴はどのあたりにあるのか?
→木が人間の二の腕より太い部分から入るので、そこまで先端からは出入りしない。
・穴の向きは決まっているのか?
→基本的に最初は横方向に掘っていって、入ったら縦横無尽に食い散らかすことが多い。
・虫が入る時期は?
→夏前に入って夏に木を枯らす。冬にその木の中で卵を産み、春に飛び立つ。
・耕作放棄地などあるが、山はちゃんと相続されているのか?
→所有者不明の山林が九州の面積と同じくらいある(相続されていない)
一方で、栃木県の林業従事者は300名しかいない。
・虫が入った木を全部切れば解決するのか?
→進行を止めていくという解決方法しかない。
・山の所有者はナラ枯れを認知しているのか?
→所有者が把握しているケースはほとんどないと思う。
課題に対するアイデア
・固定資産税に関する通知を送るときに、ナラ枯れ問題のことも併せて周知できたら山の所有者にも認知が広まるのではないか。
・森林を知らない人に向けて、課題について周知していく必要もあるかもしれない。
・宮ココのような仕組みを活用してはどうか?撮った写真を共有して緯度経度がわかれば、対策が必要な木がある場所にいけるのではないか。
・山岳部の学生等に、社会的なアクティビティとして、森の木を調査するキャンペーンに参加してもらうのはどうか。
感想
・携わったことがない分野だったのでわからないことが多かったが、紅葉の時期ではないのに葉の色が変わっているところがナラ枯れだったというのは知らなかった。課題解決のためには、まず認知を広めていくことも重要なことだと感じた。
・県域で、参加したくなる要素も加えた市民参加型のイベントができたら、山に興味を持つ人が多くなると思う。
・ナラ枯れに対する課題感に気付くことができてよかった。進めていく方向性はたくさんあると思う。
・住んでいるところの近くにナラがあるので身近に感じることができた。そこが枯れたら景観を損なうので大変なことだと思った。
投稿者コメント
・普段は山にいることが多く、なかなか異業種の方と話す機会がなかったので嬉しい機会だった。
知らない人に山のことや木のことを理解してもらおうと話していく中で、自分の中で改めて整理されることがあったのでとても有意義な場だった。
今後も話し合いながら進めていきたい。