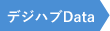レポート作成日:2025/07/28
第18回課題深掘り会レポート【県境を越えたまちづくり~若者や地域外の人も関わりやすい情報共有や合意形成の仕組みを考えたい~】
1.課題について
背景:
・栃木市と事業構想大学院大学の連携プロジェクトに参画中。
・投稿者自身はデイサービスを運営し、高齢者の元気づくりを通じた地域活性化を目指している。
構想:
・2026年3月に廃校予定の寺尾中学校を多世代交流の居場所として活用
・廃校利活用のアイデアとして、獣害対策としてイノシシや鹿をジビエとして加工・価値化
・廃校にデイサービス、障がい者施設、フリースクール、就労支援などを集約し、コミュニティ支援や新たなチャレンジの場を創出
・Web3.0やDAO(自律分散型組織)などデジタル技術を活用し、地域内外の多様な人々が関わりやすいコミュニティ形成や情報共有、合意形成の仕組みを構築できないか。
課題意識:
・地域住民(内部者)と外部者との間に存在するコミュニケーションの壁や、外部者が関わりにくい独自の文化があること
・既存の自治会組織のあり方に対するアップデートが必要
・投稿者自身のWeb3.0/DAOに関する知識・理解不足
・合同会社DAO形式でのジビエ事業立ち上げの実現可能性
・地域住民へのWeb3.0/DAOの理解促進方法
目指す姿(10年計画):
・地域内外の人がWeb3.0等のデジタルを通じて様々な活動に関わることで、廃校を拠点とした地域が活性化する
・地域を離れた卒業生などが、デジタルを通じて継続的に関われる
・廃校での成功モデルを、他の地域にも展開可能な組織モデルとして構築
2.技術についての基本的な解説:Web3.0とDAOの可能性
株式会社ジード代表取締役 武田文夫氏より、Web3.0およびDAOに関する基本的な解説がありました。
Web1.0からWeb3.0への進化:
・Web1.0 (1993年頃~2000年代前半):
一方向の情報発信(専門業者によるホームページ作成が主)
・Web2.0 (2005年頃~現在主流):
双方向の情報発信(Facebook、ブログ等)。データはGoogle、Facebook等の特定企業が集約管理。
・Web3.0 (現在進行形):
双方向かつ分散型のデータ管理。ブロックチェーン技術を基盤とし、中央管理者を必要としない。
ブロックチェーンとNFT:
・ブロックチェーン: データを鎖のように繋ぎ、多数の場所に分散して保存する技術。改ざんが極めて困難。
・スマートコントラクト: ブロックチェーン上で契約条件を自動実行する仕組み。
・NFT (Non-Fungible Token): デジタルデータに唯一無二の価値(所有権など)を証明する技術。デジタルアートや会員権などに応用可能。
DAO (Decentralized Autonomous Organization):
・自律分散型組織。特定の管理者や中央集権的な意思決定機関を持たず、参加者それぞれが自律的に活動し、共通の目標達成を目指す組織形態。ブロックチェーン技術が基盤となることが多い。
AIとの関連:
・AI技術の進化(特に大規模言語モデルLLM)とWeb3.0が融合することで、よりリアルな仮想空間体験や、AIエージェントとの協働などが可能になる未来も予測される。
3.課題解決に向けたアイデアと提案
参加者による意見交換では、課題に対し以下の具体的なアイデアや視点が提供された。
・NFTを活用し、地域への関与や貢献を証明する「デジタル住民票」の発行アイデア。これにより居住地に関わらず地域との繋がりを可視化・強化できる。
・遠隔地にいても地域の風景や雰囲気を感じられる情報発信。
・地域活動への参加や貢献に対し、金銭的報酬だけでなくNFTや地域独自のポイント、特典などのインセンティブを付与する仕組み。
・学生やUターンした女性など、多様な層がフラットに参加しやすく、そのアクションが評価される設計の重要性。
・ジビエ事業や廃校運営を担う地域商社を、合同会社とDAOの概念を組み合わせた形態で設立すれば運営負担を分散し、多くの関係者が主体的に関わることができるのではないか。
・廃校を拠点に、ジビエの加工・商品開発(ペットフード、革製品等)だけでなく、そのプロセスに多様な人々が関わる。
・地域の中小企業のマーケティングやPR支援を、DAO的な仕組みで地域内外の人材(プロボノ、学生インターン等)がシェアしながら行う。
・地域住民との丁寧なコミュニケーションと合意形成、既存の地域活動との連携・歩み寄ることが重要。
4.プロジェクト推進における留意点と懸念事項
議論の中で、プロジェクトを効果的に進める上での重要な視点や潜在的な課題も指摘されました。
・目的・ゴールの明確化: プロジェクトが「誰のために」「何を目指すのか」(ミッション・ビジョン・バリュー)を明確に設定する必要性。
・住民理解と巻き込み: Web3.0やDAOといった新しい概念について、地域住民に分かりやすく伝え、理解と協力を得ることの重要性。IT技術が先行し、住民が置き去りにならないような配慮。
・実現可能性の検証: ジビエ事業の許認可、加工技術、販路確保などの具体的な課題への対応。
・多様なステークホルダーとの連携: 行政、地域住民、企業、専門家など、多様な関係者との効果的な連携体制の構築。
5.参加者感想
・素敵なアイデアが多く出てきたと思う。まずはゴールを1つ決めた方がいいと感じた。その結果人が集まりやすくなるし、意見も絞りやすくなると思う。
・自治会に参加する人は年々減っているので、地域にいなくても参加できる仕組みはとてもいいと思った。
・興味のあるテーマだったが、誰のためのテーマなのかというところで会話についていけない場面があった。IT技術が先走って地域の人を置いていかないように丁寧に進めてほしい。
・いろいろ規定があるところに新しい風を吹かせるのは大変だと感じた。
・特徴的な地形とか産業がある地域。麻を作っている畑もあるし。地元の人はずっと住んでいるから魅力に気が付いていないこともあると思うので、外部の声と地元の方の意見を組み合わせながら地域活性化ができたらいいのではないか。
・自立的分散組織の効果的な活用について考えるいいきっかけになった。
・とても勉強になった。地域のコミュニティの活性化は高齢者が元気に長生きするためにも必須だと思う。
・実際に廃校活用をしていくことに魅力を感じた。
・社会が拡張したり縮小したりするのは必然だと思っている。社会生活がそれぞれの理想に基づいて構成されていることが理想だと感じた。
・課題ページを見たときはどのように展開していくのかわからなかったが、今日話を聞いて、面白い未来に繋がっていくプロジェクトなのではないかと感じることができた。