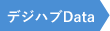レポート作成日:2025/10/28
第19回課題深掘り会レポート【災害時に孤立する中山間地域への対応と被災者支援】

話題提供:フードバンクあしかがの活動と災害支援への展開
フードバンクの概要と活動実績
・フードバンクの定義
まだ食べられるが廃棄される食品を預かり、必要とする人へ無償で届ける活動。全国に約300〜400団体、栃木県内には約12団体が存在するが、県内市町の約半数にはフードバンクがない。
・フードバンク足利の活動モデル
食品調達元:
企業(備蓄入れ替え品)、食品製造業(外箱破損品)、家庭(余剰食品)など。
提供先と連携:
制度の狭間にいる人々
⇒制度に繋げる事ができる人が訪問するきっかけとして食品を提供し、相談しやすい関係構築を支援。
多様な困難を抱える人々
⇒社協、地域包括支援センターや民生委員と連携し、精神疾患や障がいのある方、ひとり親家庭などを支援。
被災地
⇒全国フードバンク推進協議会と連携し、能登半島地震の被災地へ食品やマスクを送付。
こども食堂
⇒閉店間際に来る家庭向けに、持ち帰り用のお土産(レトルトカレー等)を提供。
・連携体制と評価:
自治体、社会福祉協議会、地域包括支援センター、民生委員など多様な主体と連携し、「食」を核とした支援ネットワークを構築。この体制が評価され、昨年度「輝く栃木づくり表彰」で最優秀賞を受賞。
・フードバンク専用保険:
2023年10月より、全国フードバンク推進協議会が被保険者となる「フードバンク保険」が開始され、各団体は安価に必要な保険へ加入可能になった。
運営上の課題と災害時備蓄の現実
・寄付で集まる食品で運営されるため、種類や量は予測不可能。「夏におでん、冬にそうめん」が届くなど、需要と供給が一致しないことも多い。また、マンパワーも不足しており、食品の取扱い量は年間10トン程度に留まる。
・フードロス対策で集まる食品には賞味期限が近いものが多く、災害用の長期備蓄には向かない場合がある。例えば、寄付で提供された賞味期限間近のアルファ米をそのまま災害用に再備蓄するのは難しい。
上記の理由から、フードバンク単独で中山間地域の防災備蓄を全て担うことは困難であり、「少しでも足しになれば」というスタンスでの協力が現実的である。
中山間地域における災害時食料支援に関する提案
・栃木県南エリアなどの中山間地域は、川沿いに集落が形成され、その裏手は山という地形もあり、崖崩れなどで道路が寸断されると容易に孤立するリスクがある。
具体的な提案:フードバンクのサテライト倉庫設置:
災害による孤立の可能性がある集落内、中山間地域に食料を備蓄し、外部からの物資輸送が困難になった際のセーフティネットを構築する。
運用コンセプト
- 発災時:道路寸断時に、自治会長などが管理し住民で食品を分け合う。
- 平時: 地域内で生活に困窮している人への支援にも活用する。
- 柔軟な運用:食品は民間の寄付であるため、厳密な管理は求めず「臨機応変に使ってほしい」という方針で運用する。
話題提供への質問と議論
備蓄倉庫(サテライト倉庫)の設置場所と運用
フードバンクあしかがの備蓄倉庫は足利市中心部に2箇所あるが、中山間地域には存在しない。
新規で備蓄倉庫を設置するとしても、コストを抑えるために、集会所や廃校、企業の倉庫や空き家等の既存空間を活用したい。
ただ、場所を設置したとしても、倉庫の管理運営には人の配置が不可欠。実際に動き出すときはハザードマップを確認し、浸水や土砂災害のリスクが低い安全な場所を選定する必要がある。大雨による災害や、夜間の災害などの状況を想定してシミュレーションし、高齢者など交通弱者の視点も踏まえ、実際に物を取りに行ける場所かどうかの検証が重要。
フードバンクに集まる品目の現状
フードバンクで集まる食品としては缶詰、お菓子、レトルトカレー、カップ麺、生米、乾麺、味噌、調味料など、基本的に常温保存可能なものが中心。食料だけでなく、それを消費するために必要な物資(紙皿等)もセットで備蓄する必要がある。
物資の在庫管理と情報の可視化
災害ボランティアセンターなどでは、多種多様な物資が乱雑に積まれ、どこに何があるか把握が困難。フードバンクでも、必要なものが届かない、不要なものが大量に届くといったミスマッチが発生しやすいので、ものづくり企業の在庫管理システムを応用して在庫を可視化できたらミスマッチを減らすことができるのではないか。
フードバンクあしかがの管理方法としては、記録⇒保管⇒出庫というやり方。まずは寄付経路を記録し、トレーサビリティを確保。「種類」と「賞味期限」で分類し、中身が見えるプラボックスで棚に保管。賞味期限が近いものを手前に配置。外箱に賞味期限を大きく記載。出庫する時は期限が近いものから、受け取る方の状況(調理環境の有無など)に応じて提供。これにより、期限切れによる廃棄はほとんど発生していない。
フードバンク向けの業務管理システムは存在するが、月額1万円程度のコストがNPOにとって大きな負担。持続可能な運営のための資金調達が課題。
議論の中で見えてきた3つの供給アプローチ
- 事前設置型(プル型):
平常時から備蓄倉庫を地域に設置し、必要な時に住民が自ら取りに来る。 - 事前配送型(プッシュ型)
災害発生が予測される段階で、支援が必要な世帯を特定し、事前に食料などを直接届ける。 - 連携配送型(ハブ&スポーク型)
フードバンクの物資を確実に届けてくれる「配る人」(市役所、民生委員、自治会長など)や「拠点」と連携する。
フードバンクの新たな役割
フードバンクの新たな役割として、平時から要支援者を把握し、発災時に避難所に来られない人々へ直接アプローチしていく動きがある。食料提供を通じて地域住民との関係性を構築することで、フードバンク自体が災害時のセーフティネットとなりうる可能性を秘めている。各自治体で個別支援計画の策定が求められているが、進捗や実効性は自治体によって差がある。中山間地域では高齢化と担い手不足により、計画があっても実行する体力が失われつつある。
新たな支援アプローチのアイデア
ドローン活用
⇒物資輸送の手段として期待されるが、現状は積載量が数kg〜10kg程度と限られ、社会実験や規制緩和が今後の課題。
消防団の活用
⇒地域住民で構成される消防団を、物資の配り手として活用する。平時の訓練に物資輸送を組み込むことで、有事の連携をスムーズにする。
参加者からのコメント
・国の指針も支援の焦点を「避難所」から「被災者」へと転換しており、避難所に避難できない人々への支援方法の確立が課題だと思った。
・フードバンクの備蓄状況と市町の備蓄状況を連携させ、食事をどう届けるかの仕組みを構築できれば、より質の高い支援が可能になると感じた。
・平時からフードバンクの食品を各地に備蓄することは難しいが、市町や自治会といった小さな単位で実行可能な取組もあるのではないかと思った。
・デジタル技術と並行し、隣近所とのコミュニケーションといったアナログな 関係構築が不可欠だと思った。
・フードバンク自身が活動を積極的に情報発信し、行政もその活動を周知する必要がある。
・平時から地域住民とコミュニケーションを取ることが、有事の際の円滑な協力体制に繋がるのだと再認識した。
・かつての「世話焼きおじさん・おばさん」のような役割を担う人材が再び必要になる可能性がある。
・困っていても「助けて」と言い出しにくい社会的な雰囲気がある。「情けは人のためならず」という言葉の本来の意味が忘れられ、助け合いの文化がより重要になると思った。
・フードバンクの資源や活動が可視化され、災害時に「自由に使ってください」と言えるシステムの構築が理想。そのためにはデジタル化と運営コストの確保が課題だと考えた。
・消防団や寺院など、地域に古くから存在する組織や場所が持つ役割を再評価し、フードバンクと連携することで新たな価値を生み出せると思った。
・地域課題があるからこそ、それを解決するためのイノベーションが生まれると感じた。